「顧問税理士って必要?」小さな会社こそ頼れる存在に
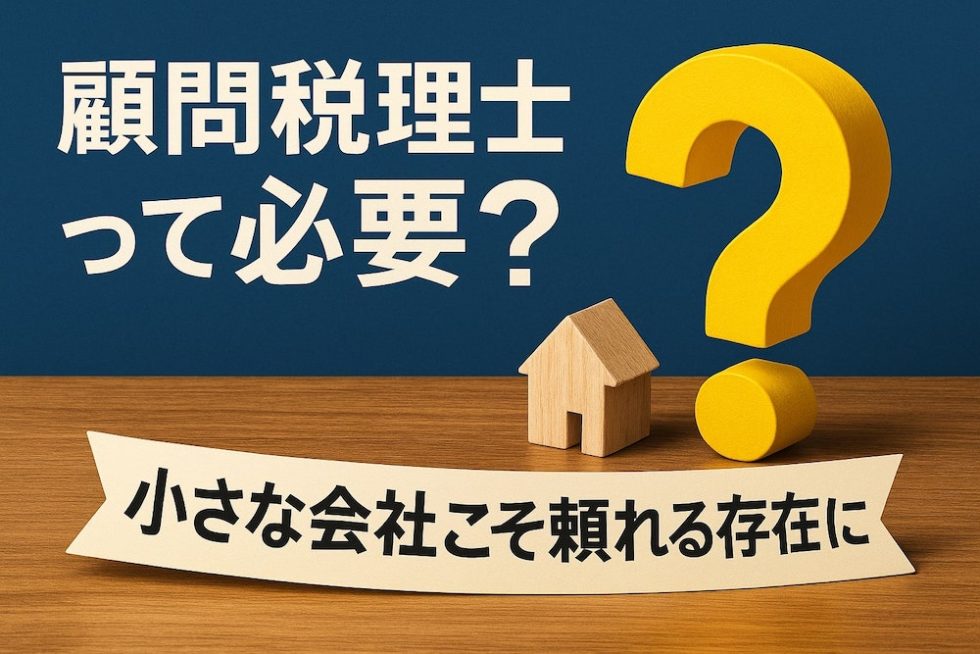
「うちの会社にも顧問税理士って必要なんだろうか?」
この言葉をどこかで呟いたことはありませんか?
小さな会社を経営していると、顧問税理士の必要性について迷う瞬間が少なからずあるものです。
確かに、コストがかかる。
でも、その先にある安心感や経営判断のサポートはどうでしょうか?
私は税理士として30年以上、中小企業の皆さんと向き合ってきました。
その中で一貫して感じるのは、会社の規模が小さいからこそ、頼れる「人」の存在が大切だということです。
「数字の向こうには、誰かの人生がある」
これは、私が駆け出しの頃に上司から教わった言葉です。
この記事では、顧問税理士の役割を「税金の専門家」という枠を超えて、小さな会社の経営者にとっての「伴走者」という視点からお伝えしていきます。
顧問税理士とは何者か?
税理士の基本的な役割とは
税理士は、税務に関する専門家として国家資格を持つ専門家です。
「税務書類の作成」「税務代理」「税務相談」という3つの独占業務を法律で認められています。
確定申告をはじめとする税務申告書の作成や提出、税務調査への立ち会いなど、税に関する業務を代行することができるのです。
特に小規模事業者にとって、専門知識が必要な税務手続きを任せられるのは大きな安心につながります。
税制は毎年のように改正され、専門家でさえ常に学び続ける必要があるほど複雑化しています。
そんな中、経営者がすべてを自分で把握するのは至難の業といえるでしょう。
顧問契約の仕組みと費用感
顧問契約とは、一定期間継続して税務指導や経営サポートを受けるための契約です。
多くの場合、毎月定額の顧問料を支払うことで、税務相談や決算手続き、資金繰りなどについて継続的なサポートを受けられます。
費用相場についてですが、現在の市場では法人の場合、月額2万円から5万円程度が一般的です。
小規模な中小企業であれば月額3万円前後が相場といわれています。
この金額は、会社の規模や業種、依頼内容、訪問頻度などによって変動します。
決算申告費用は別途発生する場合が多く、月額顧問料の4〜6ヶ月分程度が目安となるでしょう。
また、記帳代行や給与計算などもオプションとして追加することで、経理業務の多くを外部委託できます。
一般的な”顧問税理士像”とその限界
「顧問税理士=確定申告だけをやってくれる人」
この認識は、多くの経営者が持っているイメージかもしれません。
確かに、年に一度の決算と税務申告だけを任せるという関係性の税理士も存在します。
事務的に数字を処理し、書類を作成して申告するだけ。
こうした関係では、せっかくの専門家の知見が十分に活かされているとは言えません。
実際、私が見てきた多くの中小企業と税理士の関係は、「年に一度の儀式的な面談」にとどまっていることが少なくありませんでした。
しかし、これは顧問税理士の可能性の一部でしかないのです。
適切な顧問税理士との関係構築は、単なる税務処理を超えて、経営判断の質を高める重要なパートナーシップになりえます。
小さな会社にこそ税理士が必要な理由
経営者が抱えがちな”税とお金”の悩み
小さな会社の経営者にとって、「税金」や「お金」の問題は常に頭から離れない悩みです。
「今月の資金繰りは大丈夫だろうか」
「税金をもっと減らせる方法はないのか」
「会社の利益は出ているのに、なぜか手元にお金がない」
こうした疑問や不安は、日々の経営の中で常に付きまとうものです。
私が顧問をしている小さな町工場の社長は、かつてこう漏らしていました。
「夜中に目が覚めると、まず資金繰りのことが頭に浮かぶんです」
この言葉には、小規模事業者の切実な現実が表れています。
経営者一人で悩み続けると、客観的な視点を失い、時に最適ではない判断をしてしまうこともあります。
そんな時、数字に強い第三者の視点は、非常に心強い味方になるのです。
経理・申告だけじゃない!実は頼れる相談相手
優れた顧問税理士は、単なる「申告書作成係」ではありません。
経営に寄り添い、時に厳しい現実を伝え、時に可能性を示してくれる存在です。
例えば、次のような場面で力を発揮します。
1. 経営判断のための数字の見方
- 月次の試算表から読み取れる経営状況の分析
- 利益率の改善ポイントの発見
- キャッシュフローの改善策の提案
2. 金融機関との関係構築
- 資金調達のための事業計画書作成
- 決算書の見せ方のアドバイス
- 融資交渉の際の同席やサポート
3. 経営者の孤独への共感
- 日々の悩みを相談できる身近な存在
- 経営者の気持ちを理解した上でのアドバイス
- 客観的な意見による視野の拡大
小さな会社ほど、経営者は「何でも屋」になりがちです。
そんな時、専門分野をしっかりと任せられる相手がいることは、心の余裕を生み出す源になります。
税務リスクと機会損失を防ぐ存在
税務上のミスや認識不足は、思わぬトラブルを招くことがあります。
例えば、消費税の課税事業者判定を誤り、突然多額の納税義務が発生するケース。
あるいは、適用できる税制優遇を知らずに、節税の機会を逃してしまうケース。
こうした「知らなかった」が原因の損失は、小さな会社にとって致命的なダメージになりかねません。
「知らなかった」では済まされないのが税務の世界です。
実際に、ある小規模事業者は設備投資の際、税制優遇措置を知らなかったために、数百万円の節税機会を逃してしまった例もあります。
顧問税理士がいれば、こうした「知らなかった」によるリスクを大幅に減らすことができるのです。
また、税務調査の際にも、顧問税理士の存在は心強い味方となります。
税務調査官とのやり取りを代行してくれるだけでなく、日頃から適切な経理処理を指導してくれることで、そもそもの指摘事項を減らすことにもつながります。
佐伯税理士が見てきた現場のリアル
「最初は不要と思ってたけど…」よくある誤解とその後
「税理士なんて決算時期だけお願いすればいいんじゃないか」
「うちみたいな小さな会社に顧問税理士は贅沢だ」
こうした言葉をよく耳にします。
しかし、私の20年以上の経験の中で、最初は渋々顧問契約を結んだ経営者が、後に「もっと早く相談しておけばよかった」と言われるケースを何度も見てきました。
A社の社長は、創業から5年間、自分で確定申告をしていました。
ある日、税務署から調査の連絡が入り、慌てて顧問契約の相談に来られたのです。
結果として、過去の処理に多くの誤りがあり、追徴課税を払うことになりました。
「最初から顧問税理士をつけていれば、この追徴課税は避けられたのに…」
と、後悔の言葉を漏らしていました。
一方で、創業時から顧問税理士と契約し、毎月の試算表を確認しながら経営を続けてきたB社は、同業他社が苦しむ不況の中でも着実に利益を出し続けています。
違いは何か?
それは「数字を味方につけたかどうか」の差だったのです。
小さな会社の「決断」を支える顧問税理士の仕事
小さな会社の経営者にとって、「決断」の連続が日常です。
「この設備投資をすべきか」
「新しい人材を採用するタイミングは」
「取引先からの値下げ要請にどう対応するか」
こうした判断の多くは、数字の裏付けがあってこそ、適切な決断ができるものです。
私が関わった例では、ある製造業の経営者が新規設備導入を検討していました。
カタログやデモを見る限り魅力的な設備でしたが、実際の収益改善効果を試算したところ、投資回収に10年以上かかることが判明。
「思ったより長いね…」と社長。
代わりに部分的な改良で対応する方法を一緒に考え、結果として少ない投資で収益改善を実現できました。
また別のケースでは、「売上が伸びているのに、なぜか資金繰りが苦しい」という悩みを抱えた小売業の社長と月次試算表を詳しく分析。
売掛金の回収期間が徐々に長くなっていたことが判明し、回収条件の見直しを行うことで資金繰りの改善につながりました。
このように、日々の小さな決断の積み重ねが経営を左右します。
その決断を数字の面から支えるのが、顧問税理士の大切な役割なのです。
クライアントの”人間くささ”に寄り添う姿勢
税理士の仕事は数字を扱いますが、その本質は「人」を見ることにあります。
数字の向こう側には、必ず人の思いや苦労、喜びがあるからです。
私が常に心がけているのは、クライアントの「人間くささ」に寄り添うことです。
たとえば、家業を継いだばかりの若い経営者。
「父親の時代のやり方を変えたいけれど、うまく切り替えられない…」
という悩みを抱えていました。
この場合、単に税務や数字の問題だけでなく、家族関係や従業員との人間関係も絡んでいます。
こうした「人間くさい」悩みに耳を傾け、時には経営者の気持ちの整理を手伝うことも、私の仕事の一部だと考えています。
また、個人事業主として長年頑張ってきた方が、健康上の理由で廃業を考えるケース。
「一生懸命築いてきたものを、どう終わらせるか」
という重い決断に向き合う時、数字だけでなく、その人の人生に思いを巡らせることが大切です。
真の意味で経営者に寄り添える顧問税理士とは、単に「税金のプロ」であるだけでなく、こうした人間的な機微を理解できる存在であるべきだと思います。
顧問税理士の選び方と付き合い方
相談しやすさ・相性がなにより大事
「うちの会社に合う顧問税理士は、どうやって選べばいいのでしょうか?」
これは、私がよく受ける質問の一つです。
答えは意外にシンプルです。
「話していて心地よいと感じる人を選ぶこと」
なぜなら、顧問税理士との関係は単なる「業務委託」ではなく、長期的な「パートナーシップ」だからです。
何か困ったことがあった時、すぐに電話やメールで相談できる関係性が築けるかどうかは非常に重要です。
専門知識はもちろん必要ですが、「この人なら安心して相談できる」という直感的な信頼感も同じくらい大切です。
実際に私のクライアントの多くは、「佐伯さんはわかりやすく説明してくれるから」「質問しやすい雰囲気があるから」という理由で顧問契約を続けてくださっています。
税理士選びでは、初回の相談の際に次のようなポイントをチェックしてみるといいでしょう。
地域に根差した税理士事務所を選ぶことも一つの選択肢です。
例えば、神戸で税理士をお探しなら濱田会計事務所のような地元に密着した事務所では、地域特有の事情や人脈を活かした支援が期待できます。
特に中小企業の場合、同じ地域で活動する税理士は業界動向や地域経済の把握にも長けている点がメリットです。
- 質問に対して、専門用語を乱用せず平易な言葉で説明してくれるか
- こちらの話をきちんと聞いてくれているか
- 業界や事業内容に関心を持って質問してくれるか
- 連絡の取りやすさはどうか(メール、電話、オンライン会議など)
相性の良い税理士は、単なる「税金の計算係」ではなく、あなたの会社の成長を一緒に考えるパートナーになれる人です。
チェックすべき「この人に任せていいか」のサイン
顧問税理士を選ぶとき、「この人に任せても大丈夫」と判断するためのサインがいくつかあります。
長年の経験から、特に重要だと感じる点をお伝えします。
1. 業界や事業内容への理解度
- あなたの業界特有の慣習や会計処理について知識があるか
- 似たような規模や業種のクライアントを持っているか
- 初回相談で的確な質問をしてくるか
2. コミュニケーション力
- 複雑な内容をわかりやすく説明できるか
- あなたの質問に丁寧に答えてくれるか
- こちらの話をしっかり聞いて理解しようとするか
3. 提案力と誠実さ
- 過度な節税策を勧めるのではなく、リスクも含めて説明してくれるか
- 自分の専門外のことは正直に認め、適切な専門家を紹介してくれるか
- あなたの会社の将来に関心を持ち、前向きな提案をしてくれるか
「できます」と簡単に答える税理士より、「これはリスクがあります」と正直に伝えてくれる税理士の方が信頼できます。
また、初回相談の段階で、顧問契約の具体的な内容や料金体系について明確に説明してくれるかどうかも重要なポイントです。
料金が安いことだけを重視するのではなく、提供されるサービスの内容とのバランスを見ることが大切です。
顧問契約の”続け方”と”見直しどき”
顧問契約を結んだ後も、その関係性は常に育てていくものです。
良好な関係を築くためには、経営者側からも積極的にコミュニケーションを取ることが重要です。
よい関係を続けるためのポイント:
1. 定期的な情報共有
- 月次の試算表を一緒に確認する時間を設ける
- 経営上の変化や懸念点を早めに伝える
- 将来の計画や展望について相談する
2. 質問や相談をためらわない
- 「こんな些細なことを聞いてもいいのだろうか」と遠慮しない
- わからないことはその場で確認する習慣をつける
- 税務以外の経営相談も、まずは顧問税理士に相談してみる
一方で、次のような場合は顧問契約の見直しを検討するタイミングかもしれません。
見直しを考えるべきサイン:
1. コミュニケーション不足
- 質問しても返答が遅い、または不十分
- 年に一度の決算時しか連絡が取れない
- こちらからの相談に対して消極的
2. 専門性の不一致
- 会社の成長に伴い、より専門的なアドバイスが必要になった
- 事業拡大や新規事業に対応できていない
- 業界特有の問題に詳しくない
3. サービス内容の不満
- 約束されたサービスが提供されていない
- 料金に見合ったサポートを受けられていない
- ミスや遅延が多く、信頼関係が築けていない
顧問契約の見直しを考える際は、まずは率直に現在の税理士に不満や要望を伝えてみることをお勧めします。
多くの場合、コミュニケーションの改善だけで関係性が良くなることもあります。
それでも改善が見られないようであれば、新たな顧問税理士を探すことも選択肢の一つでしょう。
まとめ
「顧問税理士って必要?」
この問いに対する答えは、小さな会社であればあるほど「Yes」だと私は考えています。
顧問税理士の本質は「税金の計算係」ではなく、「経営の伴走者」にあります。
税務申告はもちろん、日々の経営判断を数字の面からサポートし、時に厳しい現実を伝え、時に新たな可能性を示してくれる存在です。
特に、経営者一人で多くの判断を下さなければならない小さな会社にとって、客観的な視点を持つ専門家の存在は、想像以上に心強い味方となります。
税理士との関係は、単なる「業務委託」ではなく、長期的な「パートナーシップ」です。
相談しやすさや相性の良さを重視し、お互いに信頼関係を築いていくことが何より大切です。
もし現在、税務や経営の不安を抱えているなら、まずは一度、顧問税理士に相談してみることをお勧めします。
「わからない」「不安」を放置せず、信頼できる専門家と一緒に一歩踏み出すことが、会社の未来を切り拓く第一歩になるのではないでしょうか。
数字の向こうには、あなたと従業員の人生があります。
その大切な人生を守り、より豊かにするために、顧問税理士という「人」の力を借りる選択を、ぜひ前向きに検討してみてください。



